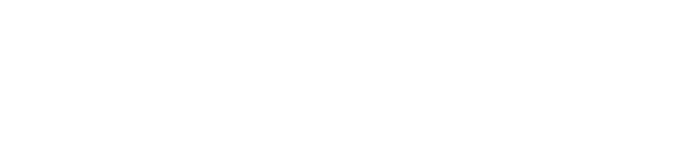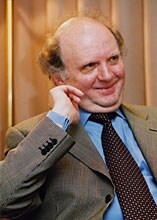TDKオーケストラコンサート2003
TDKは、2001年より世界の著名オーケストラの日本公演に協賛しています。
2003年は、放送交響楽団の中で最も長い歴史を持つベルリン放送交響楽団を迎え、11月18日と30日の2公演に協賛しました。この公演は、マエストロのマレク・ヤノフスキ指揮のもと、ヨーロッパ・クラシックを代表するベートーヴェンの楽曲に絞った「ベートーヴェン・プログラム」で行われました。
また、11月30日には本公演に先立ち、今年も「Specialリハーサル」と称した公開リハーサルを開催しました。これは、小学生から社会人まで音楽を学んでいる方々を、本公演前に実際に行われるリハーサルにご招待し、世界的なオーケストラと指揮者による音作りの過程を体験してもらうものです。
TDKでは、2004年以降も世界的なオーケストラの日本公演への協賛を継続していく予定です。
Specialリハーサル
小学生から社会人まで音楽を学んでいる方々に、世界的なオーケストラと指揮者が音楽を創造していく過程を体験してもらう公開リハーサルプログラムです。今年は一般公募の200名様ご招待に加え、新たに100名の団体公募を行いました。昨年にも増してたくさんのご応募があり、個人で楽器を習っている方、学校の部活動やアマチュアのオーケストラに所属して勉強されている方などがいらっしゃいました。
そして、今年は特にオーケストラと参加者が交流することのできたリハーサルになりました。というのも、指揮者ヤノフスキ氏のご配慮で、舞台間近で鑑賞することができ、また通訳を介してリハーサルのねらいや楽曲の聴きどころをわかりやすく説明していただいたからです。厳格そうな顔立ちのマエストロが、普段着姿で時にはユーモアを交え、熱心に参加者に語りかけるので、皆笑ったりうなずいたり。団員の方も皆、和気あいあいという雰囲気で、終始和やかなムードが漂いました。
TDKでは、2004年以降も「Specialリハーサル」を実施していく予定です。
「Specialリハーサル」を鑑賞された方の感想(会場でのアンケートより)
「眺めるだけのリハーサルではなく、指揮者が大変サービス精神旺盛で、まるで音楽教室のようでした。 」(20代、女性)
「本番前のリハーサルがいかに重要であり、精神面においても大変なものであることが解りました。リハーサルといえども、素晴らしい演奏でした。 」(10代、女性)
「細かいタイミングの調整などが見られてよかったです。 」(20代、男性)
「ドイツの人達は何事にも冷静で厳しいと思っていましたが、ステージから笑顔が見られ、団員同士和気あいあいの雰囲気で人間的な繋がりを感じました。 」(50代、女性)
「音楽を身近に感じ、涙が出るほど感動しました。このようなリハーサルをぜひまたお願いします。 」(60代、男性)
指揮者インタビュー (マレク・ヤノフスキ氏)
—本日の公開リハーサルはいかがでしたか?
本日ご来場いただいた日本のファンの方々は大変熱心に聞いていただいたと思います。私がリハーサルのねらいや内容を説明するたびに、うなずく方が多く、よく理解し興味を持って聞いていただいた様子が伝わってきました。リハーサルを公開することはとても良いアイディアで、ぜひ、これからも続けるべきです。音楽を勉強する方にとっては貴重な経験になると思います。
—日本ではリハーサルを公開することは珍しいですが、欧米ではいかがでしょうか?
アメリカではボストンで1度公開したことがあります。ヨーロッパでは何回も公開しており、私のいるベルリンでもよく行いました。リハーサルの公開の仕方は指揮者によって色々なやり方があると思いますが、私はいつも、リハーサルを聞いていただく皆様に、内容をできるだけわかりやすく説明するよう心がけています。
—日本のファンの方にメッセージをお願いします。
これからも心から感動してコンサートを聞いていただけることを望みます。今回のコンサートツアーは、ベートーベンの曲だけに絞って行いましたが、一つの文化を担うオーケストラにとって、作曲家を一人に統一したことはとても意味があることだと思います。それから、ドイツクラシックのモーツァルト、ベートーベン、シューベルトは音楽史上重要な作曲家であり、彼らの音楽はまじめで純粋です。音楽を聞く方にも学ぶ方にも大切に聞いていただきたいと思います。
—どうもありがとうございました。
アウトリーチミニコンサート
2003年11月19日、ベルリン放送交響楽団の金管楽器奏者5名が、東京都大田区立馬込中学校を訪れました。全校生徒と保護者および学校近隣の方総勢250名の前で、クラシックの名曲からセサミ・ストリートの音楽、フランク・シナトラメドレーといった親しみやすい曲を演奏。合間には楽器の構造についての説明などで会場を沸かせました。演奏後、生徒代表から御礼の花束贈呈と英語のスピーチが贈られました。生徒からは、「素晴らしい演奏を聴けて、またためになる楽器の話もしてくれて、とても面白かった」との感想が多く寄せられ、普段の授業とはまた違った音楽活動に関心を持ってもらえたようです。
本公演
| 名称 | TDK オーケストラ コンサート 2003 |
|---|---|
| 招聘元 | 株式会社 ジャパン・アーツ |
| 特別協賛 | TDK株式会社 |
| 出演 | ベルリン放送交響楽団 |
| 指揮 | マレク・ヤノフスキ |
| ソリスト | ペーテル・ヤブロンスキー(ピアノ)、竹澤恭子(ヴァイオリン) |
| 2003年11月18日(火) 午後7時開演 | ||
|---|---|---|
| 会場 | サントリーホール(東京都港区赤坂1-13-1) | |
| 主催 | 株式会社ジャパン・アーツ | |
| 指揮 | マレク・ヤノフスキ | |
| 曲目 | ベートーヴェン 「エグモント」序曲、 ピアノ協奏曲第5番「皇帝」(ピアノ/ペーテル・ヤブロンスキー)、 交響曲第6番「田園」 |
|
| 2003年11月30日(日) 午後2時開演 | ||
|---|---|---|
| 会場 | サントリーホール(東京都港区赤坂1-13-1) | |
| 主催 | 株式会社ジャパン・アーツ | |
| 指揮 | マレク・ヤノフスキ | |
| 曲目 | ベートーヴェン 序曲「レオノーレ」第3番、 ヴァイオリン協奏曲(ヴァイオリン/竹澤恭子)、 交響曲第7番 |
|
出演者の紹介
ベルリン放送交響楽団
1923年、ドイツ初の放送交響楽団として創設された。放送交響楽団の中で最も長い歴史を持つ。チェリビダッケ、アーベントロートをはじめとする歴代の首席指揮者、そしてクレンペラーやワルターなどの客演指揮者によって育てられた。ベルリンに多数あるオーケストラの中でも多彩な音色と豊かな表現力、そしてドイツの伝統と現代的感性の融合性を持ち合わせ、多くの市民から愛されている。今回の公演は、2002年9月から新音楽監督&首席指揮者を務めるマレク・ヤノフスキによる初の日本公演となっている。
マレク・ヤノフスキ(音楽監督、首席指揮者)
1939年ワルシャワに生まれ、ドイツへ移住。初め数学を専攻したが、後にケルン音楽大学に進み、さらにウィーンやシエナのキジアーナ音楽アカデミーでも研鑚を重ねている。指揮についてはサヴァリッシュの門下である。アーヘン、ケルン、デュッセルドルフの市立劇場の副指揮者を務めた後、1964年にケルン歌劇場の第1指揮者、1965年にデュッセルドルフのライン・オペラの第1指揮者となり、1969年~74年にはハンブルク国立歌劇場の首席指揮者、1975年からドルトムント市の音楽総監督として活躍した。1986~90年ケルンのギュルツェニヒ管弦楽団の音楽監督、さらに1984年からはパリのフランス国立放送フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者となり、89年から2000年までは音楽監督のポストにあった。
2000年7月からはモンテカルロ・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督、2001年1月からはドレスデン・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督、さらに2002年秋よりベルリン放送交響楽団の首席指揮者に就任した。オペラ、コンサートの両サイドで着実に評価を高めてきた実力派の指揮者である。
ペーテル・ヤブロンスキー(ピアノ)
1971年スウェーデンに生まれ、幼い頃からパーカッショニストとしての才能を開花させた。世界のオーケストラとの共演で飛び回り、注目されるピアニスト。1996年にはスウェーデンの国際振興に寄与した功績を認められ、スウェーデン貢献大賞を受賞。1998年にはワルシャワの秋音楽祭において、彼のために作曲されたキラールのピアノ協奏曲を初演し、この演奏に対してオルフェウス賞が贈られた。日本でもNHK交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団他と共演、多くのファンを持つ。
竹澤恭子(ヴァイオリン)
3歳よりヴァイオリンを始める。1986年第2回インディアナポリス国際ヴァイオリン・コンクールで圧倒的な優勝を飾り、それ以来"世界のKYOKO TAKEZAWA"として国際的スターダムを昇り続けている。日本の主要オーケストラには、国内はもとより海外ツアーのソリストとして度々抜擢されているほか、海外でも数々の著名なオーケストラと共演。1993年第3回出光賞受賞。1999年度愛知県芸術文化選奨文化賞を受賞。使用楽器は1707年製ストラディヴァリウス"ハンマー"。現在ニューヨーク在住。